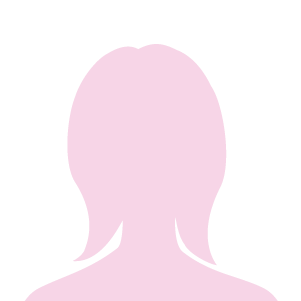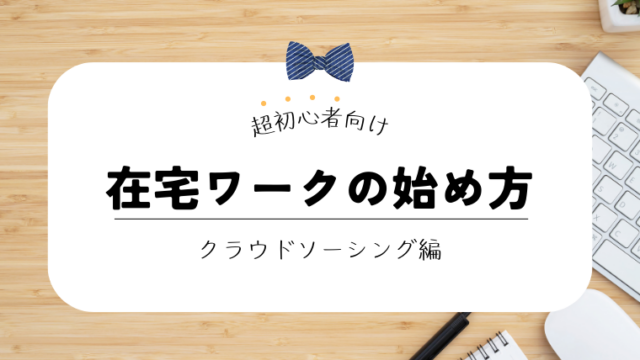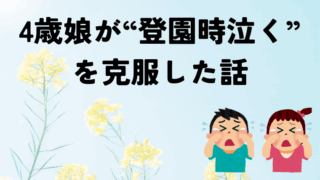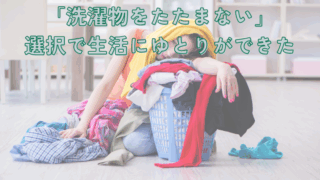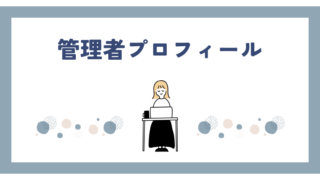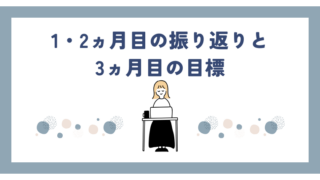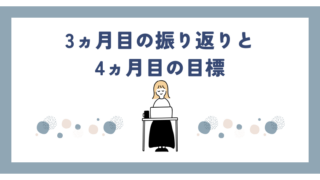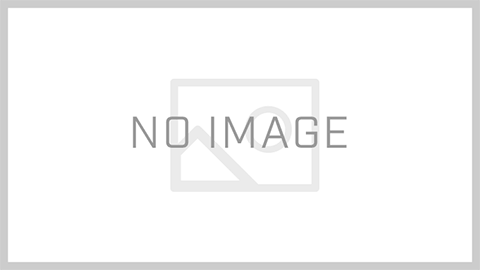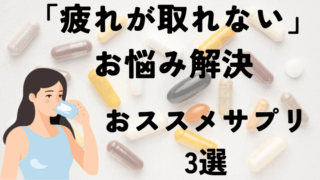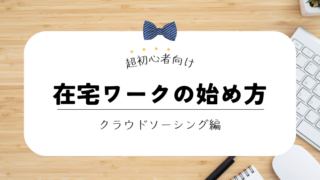「時短勤務をする予定だけど、給料はどのくらい減るんだろう?」
「時短勤務中に活用できる制度を知りたい」
「具体的な手取り額をシミュレーションしたい」
こういったお悩みありませんか?
子どもの保育園入所が決まり、ほっとしたのもつかの間。
今度は育休から職場復帰する時。
嬉しいような、悲しいような、複雑な気持ち。
時短勤務ができるのはありがたいけど、給料が減るのはかなり不安ですよね。
ただでさえ、「仕事と育児の両立」や「子どもが保育園に慣れるだろうか」と不安なことがたくさんあるのに。
せめて給料だけは、どのくらい減るのか前もって知っておけば、心の準備ができます。
・具体的な手取り額をシミュレーション
・時短勤務の時に知っておきたい制度
不安要素を一つでもなくし、気持ちよく職場復帰できるようにしましょう。
週5日勤務の時短勤務正社員という働き方から、パート+在宅副業に働き方を変えました。
在宅副業で月収10万円を目指し、スキルを磨く日々です。
今回は、2回の育休~職場復帰の経験を踏まえて、時短勤務の給料についてシミュレーションしていきます。
時短勤務の給料はどれくらい減る?|計算シミュレーション

「時短勤務ってどのくらいお給料が減るの?」
これは、復帰前に一番気になるポイントですよね。
時短勤務になると、基本的には「働く時間が短くなる=給料も減る」という仕組みです。
ただし、「ざっくり○割減る」という単純なものではなく、いくつかの要素が関わってきます。
時短勤務時の基本給の計算方法
時短勤務時の基本給の計算方法はこのように行います。
通常勤務の基本給×時短勤務の所定労働時間÷通常勤務の所定労働時間
具体的に数字をあてはめて計算してみましょう。
【例】通常勤務の基本給が25万円、通常勤務8時間→時短勤務6時間になった場合
250,000円×6÷8=187,500円
187,500円が時短勤務時の給与額面となります。
※育児介護休業法では、1日の所定労働時間を原則として6時間としていますが、企業によって異なりますので、会社の就業規則を確認するのをおすすめします。
賞与(ボーナス)はどうなるの?
時短勤務の際、賞与は基本給と同様に勤務時間に応じて減額されるのが一般的です。ただし、賞与は法律で義務付けられていないため、各企業の就業規則によって取り扱いが異なります。
手取り金額のシミュレーション
給与額がわかったら、次は手取り額を計算していきましょう。
ざっくりどんな感じかというと、
実際に私が3年前に育休から復帰した時の給料を参考にします。
フルタイム勤務時の月給242,000円、事務職、役職なしのケース
8時間→6時間の時短勤務
フルタイム(8h)
月給:242,000円
社会保険料:34,816円
手取り:207,184円
時短勤務(6h)
月給:186,500円
社会保険料:34,816円
手取り:151,684円
手取り金額が15万円ほどになっていますね。
減るのは頭ではわかっていましたが、実際に支給されて「こんなに減るの?」と驚きました。
時短勤務により月給自体が減りましたが、手取りが少ないのは、次の2つが関係しているかもしれません。
①手取り金額が少ない原因|時間外手当の減少
育休復帰後は、時短勤務により基本的に残業をしない仕事スタイルに変わります。
残業しないので時間外手当も発生しません。
残業してはいけないというわけではありませんが、
「子どものお迎え」という次の予定があるので、残業するわけにもいきません。
産休前に残業をすることが普通の働き方になっていた場合は、育休復帰後の働き方と、かなりのギャップがあるので注意が必要です。
②手取り金額が少ない原因|控除額の変化
先ほど計算した給与額から、社会保険料や税金等を引いた金額が手取り額です。
具体的に控除される金額は、主にこの3つです。
●社会保険料:育休中は支払いを免除されていたが、復帰後は再開される
●所得税:支給額に応じて変動する
●市民税:前年の所得に対して算出されるため、育休中に収入がなければ復帰後は非課税になる可能性が高い(育児休業給付金は課税対象外)
この3つの中で一番の要注意が「社会保険料」です。
実は、給料が変わったからといって、社会保険料はすぐには変わらないことをご存じでしたか?
育休復帰後は、産休前に払っていたフルタイム勤務時の社会保険料と同じ金額が控除されます。
なぜかというと、社会保険料には改定時期があり、標準報酬月額の改定は決まった時期にしか行われないからです。
標準報酬月額とは、社会保険料の計算基準となる報酬額のことです。
基本給や各種手当(役職手当、時間外手当、通勤手当など)を含む月々の総支給額を一定の基準で等級分けしたものです。
これが、「時短勤務になって給料が下がった」と感じる最大の原因です。
ごもっともです。
実は、これらを解決するために「育児休業等終了後の社会保険料の特例」というものがあります。
この制度は、復帰後3カ月に受けた給料の平均額に基づき、4ヵ月目の報酬月額から時短勤務時の給料に見合った社会保険料に改定することが出来るというものです。
■□■□対象となる条件■□■□
・3歳未満の子どもを養育していること
・これまでの標準報酬月額と改定後の標準報酬月額との間に1等級以上の差があること
・復帰後3カ月のうち、基礎日数が17日以上ある月が少なくとも1か月あること
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
ただし注意点が!
こちらから申し出をしない限り、適用されません。
また、会社を通じての届け出が必要となりますので、会社の総務や関係部署に相談することをおすすめします。
そもそも時短勤務とは?【基本の制度と種類】

子どもが生まれて仕事に復帰した後、「フルタイムで働くのはちょっと難しい…」と感じるママやパパも多いと思います。
そんな時に利用できるのが、「時短勤務」という働き方です。
時短勤務は法律で守られた制度
時短勤務は「育児・介護休業法」という法律に基づいた制度の一つです。
正式には「育児短時間勤務制度」と呼ばれています。
この制度は、3歳未満の子どもを育てている人が対象で、希望すれば1日の勤務時間を6時間程度に短縮できるというものです。
法律では「6時間勤務(1日原則6時間、週30時間程度)」が基本とされていますが、実際には会社ごとにルールが違うこともあります。
例えば、
- 1日7時間勤務(フレックスタイム制)
- 出社、退社時間をずらす「時差勤務」
- 子どもの行事に合わせた「勤務時間の調整」など
会社独自の制度(就業規則)で、選択肢が増えている場合もあるので、復帰前に確認しておくのが安心です。
育児・介護休業法とは?
「育児・介護休業法」は、働く人が育児や介護と仕事を両立しやすくするために、国が定めたルールです。
この法律には、時短勤務以外にも以下のような制度が含まれています。
- 育児休業(原則1歳まで/保育所に入所できない等の条件で2歳まで延長可)
- 子どもの看護休暇(病気などで休める日数)
- 深夜労働や残業の免除
- 育休明けの不利益な取り扱いの禁止
2025年知っておきたい制度
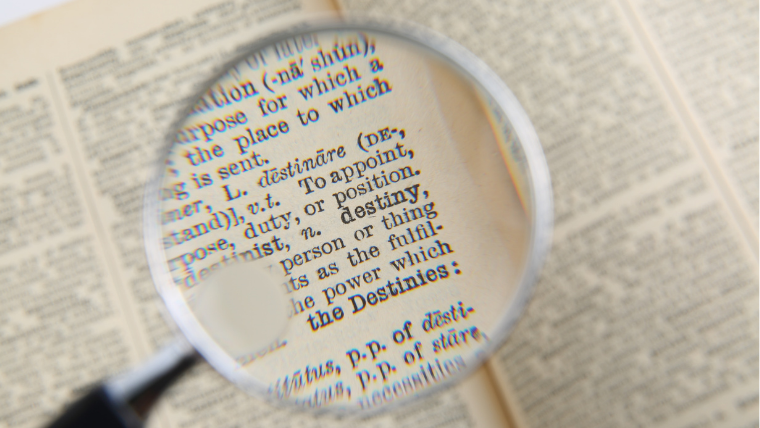
2025年は、子どもを育てながら会社で働く人を応援するような制度の改正が多くあります。
給付金の面、働き方の面で大幅に変わってくるので、しっかり確認しておきましょう。
①「育児時短就業給付金」の開始
2025年4月より新たに「育児時短就業給付金」が創設されました。
これは「時短勤務を選んだことでお給料が減ってしまった人」に対して、ハローワークから一定額が支給される制度です。
原則として育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額を支給します。
2歳未満の子を養育していることが条件なので、最近職場復帰された方は対象になるのではないでしょうか?
ぜひ職場の総務や関係部署に相談してみてください。
その他詳細な受給条件があるので、気になる方は以下のリンクからご確認ください。
②「育児・介護休業法」の改正
2025年4月1日より育児・介護休業法の改正が段階的に始まります。
主な改正は、「子の看護休暇の見直し」や「テレワークの導入」などです。
3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように、
企業側が環境を整備する努力義務を負うことになりました。
小さなお子さんを育てているママ・パパにとっては、テレワークが出来ると通勤時間が減ってかなりの時短になりますよね。
その他、いくつか改正ポイントがありますので、以下のリンクからご確認ください。
最後に

時短勤務で変わる給与から、2025年の制度改正のポイントまでを見てきました。
ポイントは、
- 手取り額が減る・増えるタイミングがあるということを知っておくこと
- 社会保険や雇用保険それぞれで免除や給付制度があること
- 法改正や会社の就業規則を把握しておくこと
疑問に思ったことは、ひとまず会社の総務や関係部署に相談することが一番のおすすめです。
時短勤務になるとどうしても給料が減ってしまいますが、
子どもが小さいうちはそういう働き方でいいのかもしれないと私は思っています。
就学前までは、ママ・パパが一番ですが、
小学生・中学生になれば、自然と一人で過ごしたり、友達が優先になっていきます。
その時にがっつり働けるようになっていればいいのかなと思います。
人によって何が大事かは異なります。
その時々で、大事だと思うことや、今しか過ごせない時間を大切に過ごしていきたいですね。
最後までお読みいただきありがとうございました。